2016年の冬至は12月21日水曜日
- hadazen
- 2016年12月19日
- 読了時間: 3分

生命の終わる冬を乗り切る為に。
日頃わたしたちは宇宙の流れや太陽について関心を向けることなく、忙しい日々を送りがちですが、一年に2回の大事なエネルギーの境目となるフォースを掴んでいきたいものです。
このエネルギーは生命体すべてに影響するものだから★
一年で最も夜が長くなる日が「冬至」で、陰陽五行説では「陰」の氣が強まるタイミングで、外界からの病氣や魔が入ってきやすい時期とされているので要注意。しっかりと体調管理をしていきましょう。毎年12月22日ごろにその日があります。
冬至は「生命の終わる時期」
だと考えられ、それを乗り越えるため、身体の無病息災の祈願などをし、溜まった心の不安を取り除こうとする行事が多々日本にはありました。最もエネルギーが弱まる冬至の日は「一陽来復」の日でもあり、転じて悪いことばかり続いたあとで、ようやく幸運に向う日とされています。
「死に一番近い日」とも言われているので、厄〔やく〕を払うために体を充分に温め、無病息災を祈って、柚子湯に入ります。 柚の香りには邪を祓う霊力があると信じられていたので、お風に入れるなどして寒く暗く長い夜を、「できるだけ楽に越せるように」という先人たちからの教えが伝え残っています。
栄養面で「柚子」は、血行を促進する成分や、鎮痛作用のある成分が含まれていますし、更にビタミンCも豊富なため、湯につかり全身からそれらの成分を吸収することで風邪をひきにくくする効果があります。
冬至は「とうじ」と読みますが、これを「湯治〔とうじ〕」とかけて生まれたのが柚子湯(柚子を入れたお風呂)とうことになります。「柚」自体にも意味があり、「融通〔ゆうずう〕が利きますように」という願いが込められているそうですので、昔の日本人は駄洒落が真面目に生活の基盤となっていて(笑)、宇宙の流れ(天)と実生活(地)の結びが、しっかりと感じられていたのでしょうね★
また日本の食文化面では、冬至には太陽の様に黄色く輝く「かぼちゃ」を食します。
弱った氣を強め、無病息災を祈るために、視覚から黄色の光エネルギーを身体に入れ、色味の野菜の少ない冬の季節に、たっぷり栄養補給します。滞りなく流れるエネルギーのトーラス構造をした「かぼちゃ」を食べ、身体のエネルギーをアップさせるのが風習です。
昔の人々は、冬至の日照時間が短いため、生命の源である太陽の恵みを享受することが出来にくく、人々は生活の不安を感じていました。特に北半球では冬至に対する不安はとても大きかったようです。
冬至は分割点
古来、冬至は新年の起点として考えられていました。というのも、冬至は一年で最も日が短く、この日を境に昼間の時間が延びていくからです。また、昼は長くなってはゆきますが、寒さは一段と厳しくなります。
中国の太陰暦で冬至は暦の起点とされ、厳粛な儀式を行っていました。日本には中世になって伝わり、宮中などで朔旦冬至〔さくたんとうじ〕という祝宴を催していたようです。
今年の冬至は12月21日水曜日になります。冬至までの闇夜が長くなる時間を楽しく過ごせる工夫をして、もうすぐ迎える新年を、「陽の氣」たっぷり迎える身体と心の準備をしていきましょう。

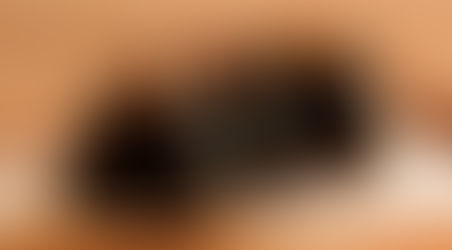





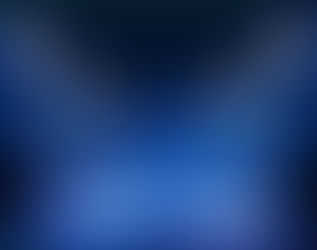
















コメント